バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の釣りたいバス釣り日記は、「バスが釣れない理由」について考えてみたいと思います。
バス釣りの現場で、突然 bite が止まる瞬間に遭遇したことはないだろうか?天候は安定、水温も問題なし、ルアーも実績十分。それでも魚は沈黙する——そんな不可解な状況に、科学がひとつの答えを示し始めていいます。
広島大学・吉田将之准教授による「こころの生物学」や、マダイを使った国際研究では、魚類にも人間のような“感情に似た状態”が存在し、それは環境刺激そのものではなく、魚自身の知覚と認知によって制御されていることが明らかになってきました。
そしてセントローレンス川で開催されたエリートシリーズでは、バーニー・シュルツがその“気分の変動”をまさに肌で感じる体験をされ、魚の反応は1時間ごとに変化し、釣り人のプレッシャーによって攻撃的な気性が一瞬で防御的に変わる——その現象は、フィールドと脳科学がつながる瞬間です。
この記事では、バスの“気分”をめぐる科学的知見と、バーニー・シュルツの実体験を交差させながら、釣り人が知っておくべき「魚のこころ」に迫っていきたいと思います。
では!! 「バスが釣れない理由は魚の気分かも?」—それを科学で説明!の始まりです(^O^)/
「バスが釣れない理由」バーニー・シュルツが体験したバスの気分の変動
先ずは、Bassmaster.comにバーニー・シュルツ氏が執筆した「Mood swings」の記事を要約してお届けします。フィッシングプレッシャーについても肌感覚での体験と対処についても書かれていますので、バスの気分の変化とそれは対応するアングラーの知恵が学べる内容です。
Mood swings
人間と同様に、バスにも気分の変動がある。捕食者であり機会主義的な摂食行動を示すとされるが、何にも誘われない時期が存在する。
状況次第で、彼らは消極的で無関心な状態にあることもある。一方で極めて攻撃的になることもある。さらに複雑なのは、こうした気分の変動が瞬時に変わる点だ。
今シーズンのセントローレンス川で開催されたエリートシリーズ大会ほど、この現象が顕著だったことはない。ターゲットは大型のスモールマウスバスだった。競技会では毎日、魚が様々なルアーやプレゼンテーションに反応する様子が変化し、時には1時間ごとにさえ変わったように見えた。
こうした気分の変動には、天候の変化、風や水流の速度、ボートの往来、そして特に釣り人のプレッシャーなど、様々な要因が影響していたと私は考えている。
バスが釣れない理由の典型的な例
競技初日の朝、私は早い番号を引いたおかげで、他の選手より先にスタート地点に到着できた。最初のキャストをした瞬間、すぐに魚が掛かった。その最初の魚をボートに近づけながらやり取りしていると、同じサイズの魚が数匹、横を泳いでいるのが見えた。彼らもまた、餌を食べる気分だったのだ。
数分後、ブランドン・パラニウクがカメラボートを従えて現れた。続いてセス・ファイダー、やがてコーリー・ジョンストンも到着した。その瞬間、魚の攻撃的な気性は完全に防御的な姿勢へと変わった。
競技中に釣りをしていたスポットは水深わずか4~5フィート(約1.2~1.5m)で、透き通るほど澄んでいた。魚の大半は75ヤード(約69m)の範囲に集中していた。ツアー屈指のスモールマウスバス釣り師4人をその狭い範囲に集め、さらにカメラボート2隻を加えれば…まあ、お分かりだろう。
本来なら餌食いの狂乱となるはずが、突然の猫とネズミの駆け引きへと変貌した…しかもネズミ側が優勢だったのだ。
数時間、食いつく気のない魚にキャストを繰り返した後、ブランドン、セス、コリーは全員撤退した。状況が徐々に落ち着きを取り戻す中、私はタックルを小型化し、より長い距離をキャストすることで、大型魚を数匹騙すことに成功した。
ビッグマウス・ブルース
ラージマウスもまた、極端な気分の変動を見せる。2月にハリス湖群で開催されたエリートトーナメントが、その好例だ。
大会初日、私はプラクティス中に簡単に釣れたエリアへ向かったが、なぜか戻った時には魚の反応が完全に止まっていた。視界が悪く魚の姿は見えなかったが、そこにいることは分かっていた。細いラインに切り替え、プレゼンテーションをゆっくりしてみたが、午後も半ばになってようやく魚が反応し始めた。そして時間が経つほど、魚のサイズは良くなっていった。
振り返れば、単に水温が上がるのを待てばよかったのだと思う。
特に早春には、数度の温度差が大きな違いを生むことが多い。フロリダ系統のラージマウスバスほど、温度変化の影響を強く受けるブラックバスの亜種はない。だからこそ我が州は「デッドワーム」の試金石となったのだ。バイトが極端に鈍い時は、ソフトプラスチックルアーを氷河のような速度で動かすのが最善策となる。
この状況は大会終盤まで続いた…少なくとも私にとっては。おそらく特定の魚や産卵段階に依存していたのだろう。産卵後の摂餌期に入った魚を見つけた釣り人は、ムービングベイトで早い段階で激しいアタリを得た。産卵中の魚を狙った釣り人は、プレゼンテーションをゆっくり丁寧にし、じっくり待つ必要があった。
気分の変動まとめ
次に水辺で釣りをしている時に魚が全く食いつかない場合、その状況が魚の気分にどう影響しているかを考えてみてください。
天候は安定しているか? もしそうなら、水温が問題ではない可能性がある。代わりに、流れの有無、水質の急激な変化、あるいはフィッシングプレッシャーなど、他の様々な理由が考えられる。これらの要因のいずれかが、アプローチの変更を必要とするかもしれない——例えば、タックルの小型化、プレゼンテーションの速度を落とすこと、あるいは釣り人と魚の間に距離を置くことなどだ。
バーニー氏の記事を読んだ後に、ボクが感じた「魚の気分」は現在どれ位、科学的に解明されているのか知りたくなり調べて見ると、魚種は違いますが吉田将之准教授の金魚の実験とScientific Reportsに掲載されたマダイを使った実験にたどり着きましたので共有したいと思います。
バスが釣れない理由のヒントになる吉田将之准教授の「こころの生物学」とは
吉田将之准教授は、広島大学統合生命科学研究科に所属する研究者で、「こころの生物学」を専門としています。彼の研究は、水産生物科学の枠を超えて、魚類を通じて人間の感情や心理の仕組みを探るという、非常にユニークなアプローチを取っています。
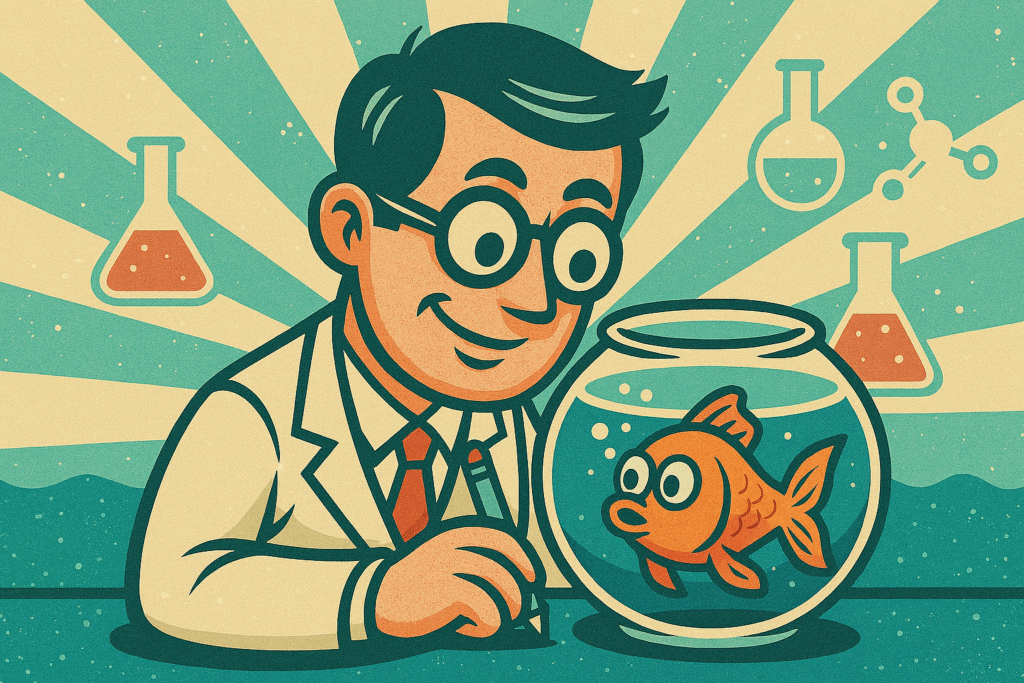
彼のアプローチは、魚の脳が人間と構造的に似ていることに着目し、よりシンプルなモデルとして魚を用いることで、感情のメカニズムを明らかにしようとするものです。
研究では、キンギョや斑馬魚などを対象に、恐怖や期待といった情動がどのように脳や身体に影響するかを観察します。たとえば、光と電気ショックを組み合わせた条件付けによって、魚が恐怖を学習し、心拍数が変化する様子が記録されます。これは人間の自律神経反応と非常に似ており、魚にも「こころ」に近い反応があることを示唆しています。
さらに、魚がエサを期待してワクワクしたり、もらえずにガッカリするような行動も観察されており、感情的な状態が脳活動に反映されることがわかってきました。鏡に映った自分を認識する魚や、睡眠中に目を動かす魚の存在も報告されており、自己認識や夢の可能性まで議論されています。
吉田准教授の研究は、魚類の行動と神経活動を通じて「こころとは何か?」という問いに迫るものであり、動物福祉や人間の精神医学にも応用可能な知見を提供しています。水の中にも、思いがけないほど豊かな“こころの世界”が広がっているようです。
吉田将之准教授によるキンギョを使った実験
吉田将之准教授によるキンギョを使った実験は、魚類の「恐怖の身体反応」を通じて、人間の感情のメカニズムを探るという、まさに“こころの生物学”の核心に迫る研究です。
この実験では、キンギョを水槽に入れ、部屋の明かりが点灯した直後に軽い電気ショックを与えるという条件付けを繰り返しました。すると、キンギョは明かりが点くだけで、電気ショックが来ることを予測し、恐怖の身体反応を示すようになります。人間なら「怖い」と感じて心拍数が上がるところですが、魚の場合は逆に心拍数が下がり、時には10秒ほど心臓の動きが止まることもあるそうです。これは自律神経による反応で、弱い動物ほどフリーズしてじっとすることで生存率を高めるという本能的な行動とされています。
さらにこの研究では、小脳のニューロン活動にも注目しており、条件付けが進むにつれてニューロンの発火頻度が変化することが確認されています。特にプルキンエ細胞の発火が、条件刺激に対して顕著に減少するようになり、これは学習によって脳内ネットワークに可塑的な変化が生じたことを示しています。
このように、キンギョの恐怖学習を通じて、感情の記憶や予測、そして脳の働きがどのように変化するかをリアルタイムで観察できるようになったのは、世界でも非常に珍しい成果です。吉田准教授の研究は、魚の“こころ”を科学的に解明することで、人間の感情や精神状態の理解にもつながる可能性を秘めています。
この研究では、魚が感じる「恐怖」や「不安」を定量的に測定する方法を開発・整理しています。魚も生き延びるために感情を持っていて、それを科学的に観察するっていうのがテーマ!ボクたちがバス釣りで与えているフィッシングプレッシャーもこの部分にあたると思います。
バスが釣れない理由のヒント!マダイを使った実験から分かって来た魚の感情!
マダイを使った「環境認知が魚に感情に似た状態を引き起こす」実験は、魚類にも人間のような情動がある可能性を探る、非常に興味深い研究があります。
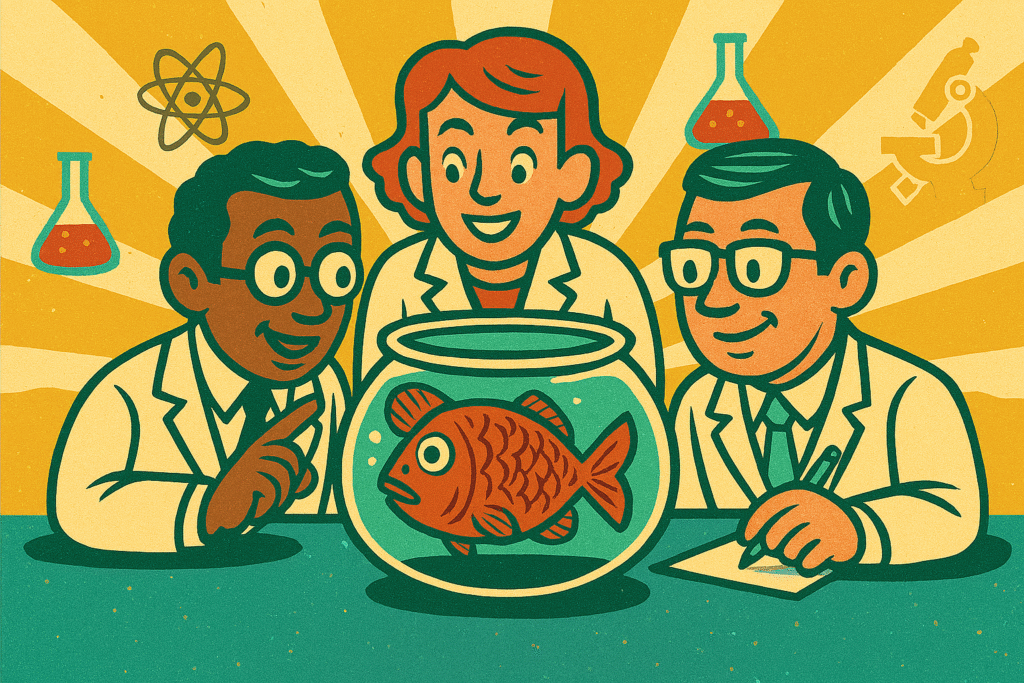
このマダイを使った実験は、M. Cerqueira、S. Millot、M. F. Castanheira、A. S. Félix、T. Silva、G. A. Oliveira、C. C. Oliveira、C. I. M. Martins、R. F. Oliveira など、ポルトガルを中心とした国際的な研究者たちが参加していて、論文はNature系列のScientific Reportsに掲載されました。
この実験では、マダイを異なる環境刺激のもとに置いて、刺激の性質(ポジティブ/ネガティブ)と予測可能性(予測できる/できない)を変化させます。すると、マダイの行動、生理機能、そして脳内の神経活動に明確な違いが現れました。
たとえば、ポジティブで予測可能な刺激を受けたマダイは、落ち着いた行動を示し、神経活動も安定していた。一方、ネガティブで予測不可能な刺激を受けたマダイは、警戒行動やストレス反応を強く示し、脳内の分子マーカーにも変化が見られた。
この結果は、感情価(快・不快)と顕著性(予測性)という2つの軸で構成される「感情空間」の理論に基づいていて、魚がそれぞれの象限に対応する異なる情動状態を持っている可能性を示しいます。つまり、魚は外部刺激をただ受け取るだけじゃなく、主観的に解釈して反応していることになるとの事です!
この研究は、魚類にも「感情に似た状態」が存在し、それを制御しているのは環境刺激そのものではなく、魚自身の知覚と認知であることを示しています。魚がただ受動的に反応しているわけじゃなくて、自分で状況を“どう感じるか”を判断しているってことなのです。
魚も主観的な世界を持っている
たとえば、同じような環境刺激——たとえば急な水流や音——があったとしても、それを「危険だ!」と感じて逃げる魚もいれば、「大丈夫」と判断して平然としている魚もいます。これは、魚が外部の刺激をただ受け取るだけじゃなく、それを“意味づけ”しているということです。
つまり、魚の反応は「刺激そのもの」ではなく、「その刺激をどう認識したか」によって変わる。これは人間の感情とすごく似てます。たとえば、同じ雨でも「恵みの雨」と感じる人もいれば「憂鬱」と感じる人もいる。それと同じで、魚も主観的な世界を持っている可能性があるってことです!
この考え方は、魚の行動を理解するうえでとっても大事で、釣りの現場でも応用できそうです。魚が今どんな気分で、どう環境を受け止めているかを考えることで、アプローチを変えるヒントになるかもしれません!
おわりに
バスの気分は、風や水温だけでなく、釣り人の存在やアプローチによっても揺れ動くとんがえるならばバーニー・シュルツの現場体験は、それを見事に証明してくれています。そして、魚類の感情研究が示すように、彼らはただ反射的に動いているのではなく、環境を“どう感じるか”によって行動を変えている事を知ることで新たなアプローチが見えて来るかも知れません。
次にフィールドへ出るときは、魚の気分に寄り添うような釣りをしてみたり、水の中の“こころ”に耳を澄ませば、これまで見逃していたバイトのサインが、きっと聞こえてくるかもしれません。
ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。
また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は無料で読むことができます。




コメント