バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、こんにちは! 今回の「釣りたいバス釣り日記」では、「釣り糸の歴史」、特にナイロンラインの誕生にフォーカスしてみたいと思います。
1935年、デュポン社のウォーレス・カロザースが「ナイロン66」を発明しました。この革新的な素材がフィッシングラインに応用されたことで、釣りの世界は大きく進化し、まさに歴史が変わった瞬間でした。
現在では、ナイロンラインに加え、フロロカーボンやPEラインなど多様な素材が登場し、タックルの組み方も自由度が増し、釣り方の幅が広がっています。
ナイロンが登場する以前は、絹糸などの天然素材を編んだ釣り糸が使われており、使用後は陰干しして丁寧にメンテナンスする必要がありました。手間はかかりましたが、釣り人たちはその道具を大切に扱っていたのです。
★ナイロン以前の釣り糸素材と歴史 古代〜中世:
日本の古代では、釣りは神事や占いの一環として行われ、武士階級にも精神的な意味を持っていた。『古事記』や『日本書紀』にも釣りの記述が見られる。平安時代には、天皇が遊びとして釣りを楽しんだ記録も残っている。
- 亜麻糸:ヨーロッパやエジプトで使用。丈夫で加工しやすく、衣料にも使われていた。
- 大麻糸:東アジアで主流。縄文時代の日本でも使われていて、水に濡れると締まる性質が釣りに合っていた。
- 絹糸(テグス):中国で養蚕技術が発達し、江戸時代には日本でも釣り糸として利用。特に「管糸」や「マガイ糸」と呼ばれる加工絹糸が人気でした。
- 綿糸:南アジアで主流。インド綿は高品質で、釣り糸にも使われます。
- 葛の繊維:日本の一部地域で使用。鹿児島県喜界島では「ハツダ」と呼ばれていた。
しかし、鎌倉・室町時代になると仏教の影響が強まり、殺生が忌避されるようになったため、釣りはあまり盛んではなくなります。
★江戸時代の日本の釣り糸:
江戸時代に入ると、幕府の安定と仏教思想の後退により、釣りは再び娯楽として広りました。特に、仕事の少ない旗本や御家人の約4割が江戸湾で釣りに夢中になっていたと言われています。
- 天蚕糸(テグス):ヤママユガの幼虫から採取。大阪の薬問屋「広田屋」が販売を始め、漁師の実演で一気に広まったという逸話もあります。
松平直矩は家臣を連れてハゼ釣りを楽しみ、これは日本最古の遊び釣りの記録とされています。また、伊達政宗も釣り好きで、フナ釣り用の池を自ら設計するほどの熱中ぶりだったそうです。こうして見ると、ナイロンが登場するまでの釣り糸は、自然の恵みと人の知恵の結晶でした。
その後、1930年代になってナイロンラインが誕生し普及するそうですが、当時は硬く扱いにくく、強度は現在のラインの半分程だったそうです。
その後、1950年代後半にナイロンラインの性能が向上し、デュポン社から、「Stren 」バークレー社から「トライリーン」が発売されます。
では!! 「釣り糸の歴史」ナイロンラインの誕生とデュポン社の功績!の始まりです(^O^)/
ナイロンを生んだ天才化学者:ウォレス・カロザースの軌跡
「ウォーレス・H・カロザース」は1896年、アイオワ州バーリントンで生まれました。若い頃から化学に興味を持ち、ターキオ大学で化学を専攻。卒業後はイリノイ大学で学び、ロジャー・アダムスのもとで博士号を取得しました。アダムスは後に彼を「国内最高の有機化学者」と称賛しています。

ウォーレス・カロザースは、分子の結合を説明する電子理論に関心を持ち、1924年には炭素の二重結合に関する論文を発表。その後ハーバード大学で教職に就きましたが、講義よりも研究に情熱を感じていました。
1928年、デュポン社から自由な研究環境と十分な予算を提示され、彼は研究所に加わります。年俸はハーバードのほぼ2倍で、優秀なスタッフも提供されました。彼はすぐにポリマーの構造と合成の研究を開始し、後にナイロンやネオプレンの開発につながる重要な成果を挙げました。
高分子理論とポリマーの研究
1928年にウォーレス・カロザースがデュポン社に加わった頃、高分子科学はまだ発展途上で、仕組みもよく理解されていませんでした。
当時、化学者たちはタンパク質やゴムなどの天然物が高分子であることを知っていて、スチレンや塩化ビニルなどから人工的にポリマーを作る実験も行われていました。1907年にはベークライトという合成樹脂が商業的に成功しています。
ポリマーが多数の小さな単位からなる巨大分子であることは知られていましたが、それらがどう結びついているかは謎でした。多くの科学者は、ポリマーは小さな分子の集まりで、弱い力で結合していると考えていました。
このような中、ウォーレス・カロザースは高分子が通常の化学結合によってつながった長い鎖状の分子であるという考えに基づき、実験を進めていきました。
1920年代初め、ドイツの化学者ヘルマン・シュタウディンガーは、ポリマーは小さな有機分子が共有結合でつながってできていると考えました。この考えは当時としては革新的で、彼は実験を通じてその理論を支持しました。
その後、カール・フロイデンベルクやミヒャエル・ポラニーなどの化学者も、シュタウディンガーの説を裏付ける証拠を発見しましたが、ポリマーの本質についての議論は1930年代まで続きました。
ウォレス・カロザースは、ドイツのシュタウディンガーとは直接の交流はありませんでしたが、ポリマーに関する考え方は一致していました。しかし、研究のアプローチはまったく違っていました。
1930年、カロザースはデュポン社の新しい化学部門責任者エルマー・ボルトンから、アセチレンを使ったポリマーの研究を依頼されました。ボルトンは応用重視の姿勢で、純粋科学を重視していた前任者スタインとは異なっていました。
ボルトンは以前から合成ゴムに関心があり、アセチレンを使ってイソプレンに似た化合物を作る方法を模索していました。カロザースは部下のアーノルド・コリンズに、ジビニルアセチレンの純粋なサンプルを作るよう指示。すると1930年、偶然にも跳ね返る固体が生成され、それが後に「ネオプレン」と呼ばれる合成ゴムの原型となりました。
デュポンは1932年にこの新素材の量産を開始し、「デュプレン」という名前で販売(後にネオプレンに改名)。天然ゴムより高価だったけれど、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れ、特殊な用途で活躍する素材となりました。
ポリマー革命:分子の鎖が繊維を変えた
ウォーレス・カロザースは、ゴムや綿などの身近な物質の構成要素である「ポリマー」に研究の焦点を定めました。当時、多くの科学者はポリマーを、小さな分子が曖昧な力で集まったものだと考えていましたが、カロザースはそれに異を唱えました。彼は、ポリマーは通常の化学結合によって端から端までつながった長い分子であると信じていたのです。
この理論を証明するため、カロザースは二塩基酸とジオールなどの小分子を使い、よく知られた化学反応を応用してポリマーを合成する方法を提案しました。こうして生まれたポリマーは「超高分子」と呼ばれ、加熱すると粘性のある透明な液体になり、冷却すると硬くて不透明な固体になるという特性を持っていました。
彼の主任アソシエイトであるジュリアン・ヒル博士は、溶融ポリマーから糸のようなフィラメントを引き出すことができること、そして冷却後にそのフィラメントを何倍にも伸ばすことで強度と弾力性が向上することを発見しました。
これらのフィラメントは乾いていても湿っていても丈夫で、繊維として非常に有望でした。また、ポリマーをクロロホルムに溶かし、粘性のある溶液をレーヨンの紡糸口金に通すことでフィラメントを製造することも可能でした。
1931年には、カロザースとヒルが線状縮合ポリマーに関する特許を申請し、米国化学会に論文を提出します。その中で、シルクよりも優れた特性を持つ「スーパーポリエステル繊維」を紹介しました。
しかし、実験を重ねる中で、得られたポリマーは融点が低すぎたり、溶媒に弱すぎたりして、繊維としての実用性に欠けていました。そのため、1933年には完全合成繊維の研究は一時停止されることになりました。
歯ブラシからストッキングへ:ナイロンが生活を変え
ウォーレス・カロザースの研究チームは、ポリエステルの合成に成功。ジュリアン・ヒルが分子蒸留器を使って高分子量のポリエステル(約12,000)を作り、冷却後に繊維を引き伸ばすことで強度と弾力性が向上することを発見しました。この「冷間引抜」技術により、分子が整列し、初の合成繊維が誕生しました。
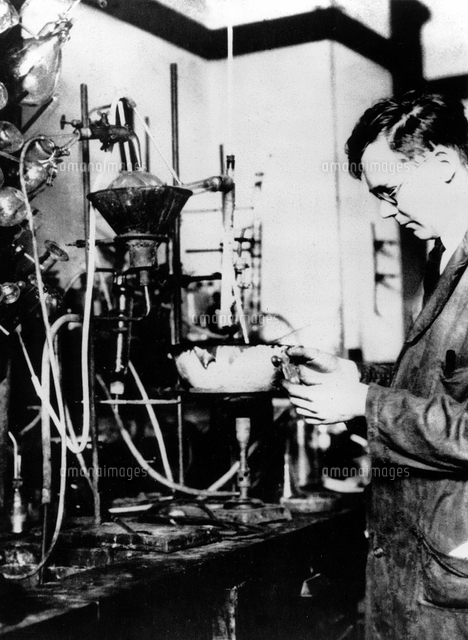
ヒルはさまざまなポリエステル繊維を試作しましたが、沸騰水や有機溶媒に弱く、実用性に欠けました。カロザースとヒルは次に、二塩基酸とジアミンを使ったポリアミドの研究に着手。初期の成果は繊維として不向きでしたが、ボルトンの後押しで研究は継続されました。
1935年2月28日、アジピン酸とヘキサメチレンジアミンから「ナイロン66」が合成されました。冷間引抜後の繊維は、強くて弾力性があり、水や溶剤に強く、融点も高いという理想的な性質を持っていました。デュポンはこの繊維を本格的に採用し、量産体制に入ります。
1936年4月30日にカロザースはナイロン素材の発明により、産業界の化学者として初めてアメリカ科学アカデミーの会員に選ばれます。
しかし、翌年の1937年4月28日にカロザース氏はフィラデルフィアのホテルの一室でうつ病により、自殺し他界します。カロザース氏の死後、1938年10月27日、ニューヨークで全国放送によりナイロンが発表されました。
最初は歯ブラシの毛や女性用ストッキングに使われ、1939年には試験販売が開始。需要は圧倒的で、販売開始から数時間で完売するほどの人気でした。
1940年5月15日には全国発売が始まり、初日に80万足が売れ、7か月後には400万足が4日間で完売。「ナイロン」は繊維の代名詞となりました。
釣り糸革命:ナイロンラインの普及と進化
1939年、デュポンはナイロンラインの販売を開始しました。しかし、最初はナイロンが硬かったため、多くの釣り人には受け入れられませんでした。
1959 年に、より柔らかく細いラインである 「Stren 」が開発されたことで、状況は変わりました。これにより釣りが容易になり、モノフィラメントラインの人気が高まりました。
丁度、同じ時期に、Berkley社からナイロン素材のフィッシングライン、Trilene(トライリーン)を市場に送り出すことに成功します。
先見の明があったバークレイ氏は、デュポン社にライセンス料を払ってライン部門に参入し、自社でナイロンラインの製造が出来るように機械の開発をはじめます。当時のナイロンラインの製造装置のプロトは、洗濯機や自転車の車輪の部品などを流用し作られたモノでした。
当時のモノフィラメントラインの価格はスプールあたりわずか 5 ドルだったそうで、安価で強度が向上した事で、天然素材のラインからナイロンラインに劇的に変わっていきました。
銀鱗の衝撃:東レが切り拓いた国産ラインの未来
1941年に日本で東洋レーヨン(現・東レ)の星野孝平らにより合成された「ナイロン6」をもとに東洋レーヨン、現在の東レがナイロンラインの開発に成功します。1942年にナイロン糸を「アミラン」として商品登録します。
1947年に日本初のナイロンライン「銀鱗」を発売します。「銀鱗」は、東洋レーヨンが戦後に発売したナイロン製の透明釣り糸で、強度・透明度・柔軟性に優れていて、当時の釣り人たちにとっては夢のようなアイテムでした。当時は広告すら必要ないほど売れたそうです。
「銀鱗」は今でも東レから発売されていて、綛巻(かせまき)タイプの台紙付き釣り糸として、漁師さんたちに愛され続けているそうです。
日本の技術がアメリカのフィッシングラインに相乗効果をもたらす!
1985年になると日本製素材コポリマー(共重合体)を採用したラインが登場します。この日本製のフィッシングラインをバグリーベイトカンパニーが「Silver Thread Blue Label」として販売した事で全米ラインメーカービック2に挑みラインメーカーに激震が走ります。
クオリティで大幅にSilver Threadに負けている事を知ったバークレー社は、Silver Thread発売からわずか3か月で、開発を進めてトライポリマーライントライマクスを販売します。
最初はタカをくくっていたデュポン社も、日本からラインを輸入し販売せざるを得ない状況になってしまいライン開発に力を入れる事になります。
これ以降、アメリカのラインメーカーはラインクオリティーに置いて切磋琢磨する事になります。
おわりに
ナイロンラインの誕生は、単なる素材の進化ではなく、釣り文化そのものを塗り替える大きな転換点でした。ウォーレス・カロザースの情熱と科学の力が、今もなお釣り人の手元に息づいていると思うと、なんだか胸が熱くなります。
ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。
また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。
「釣り糸の歴史」ナイロンラインの誕生とデュポン社の功績!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。
では!! よい釣りを(^_-)-☆
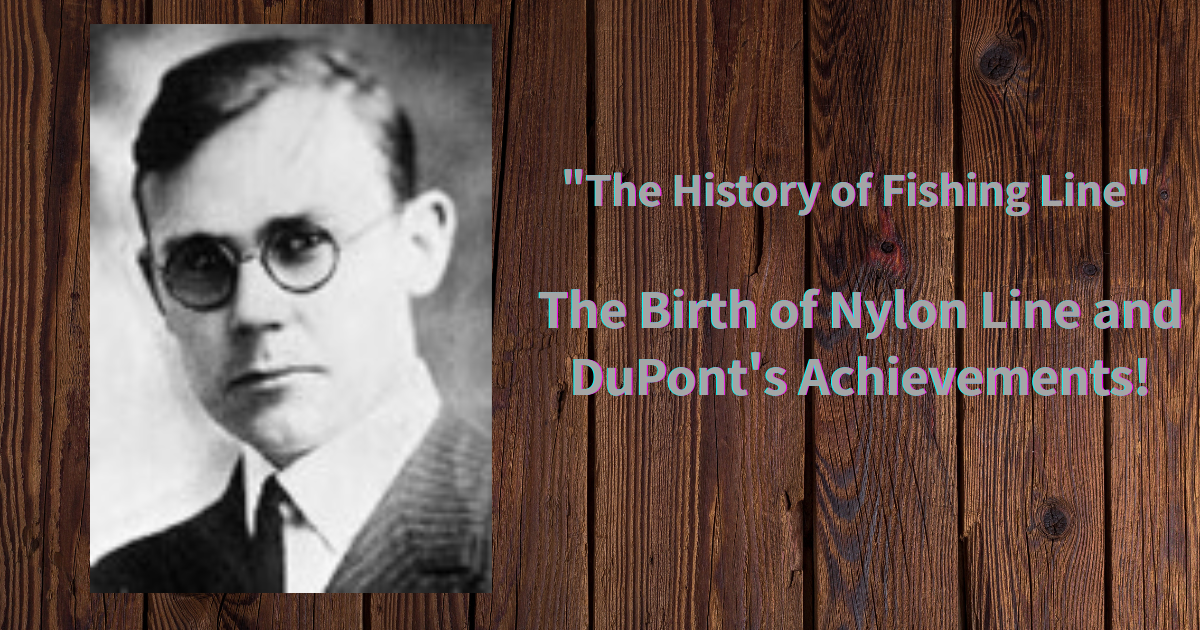
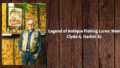

コメント