今回の「釣りたいバス釣り日記」では、釣り用語について解説したいと思います。日常的に耳にする「釣り人」という言葉を英語に訳すと、一般的には「Angler(アングラー)」と訳します。
釣り人という表現には、複数あります。「Angler(アングラー)」、「Fishing person(フィッシングパーソン)」、そして「Fisherman(フィッシャーマン)」などがその例です。それぞれの言葉にはニュアンスがあり、使い方や意味合いにも微妙な違いがあります。
例えば、「Fishing person」はそのままの意味で、単に「釣りをする人」というニュアンスを持つシンプルな言葉です。一方で、「Fisherman」は漁師という意味も含むため、魚を取ることを職業としている人を連想させます。そして、「Angler」は釣り人を意味するのですが、どこか高貴さを感じさせ、釣りに対する考え方やスタンスに深さを求められるイメージがあります。
この違いをさらに明確にしているのが、アメリカのバス釣りルアーメーカーであるコットンコーデル社の創業者が語った内容です。彼は、「Fishermanは単に魚が釣れることを喜ぶ次元に留まる釣り人であり、Anglerは釣りに哲学的な深みや美学を持つ釣り人だ」と語っています。この視点は非常に興味深く、釣りそのものに対する考え方が浮き彫りになります。
さて、あなたは「Angler」それとも「Fisherman」?この記事を通じて、釣り人としての新しい側面を発見していただけると嬉しいです。
コットンコーデルが問う! あなたはAngler? それともFisherman?
実は、一つ興味深い話があります。アメリカの著名なバス釣りルアーメーカー「コットンコーデル社」にまつわるものです。
コットンコーデル社は、ルアービルダー界の“ダビンチ”とも称される偉大な創業者、コットン・コーデル氏によって設立されました。釣り界のレジェンドともいえる彼は、釣りに関わる人々を「Angler」と「Fisherman」という二つの言葉で線引きし、その違いを鮮明に表現しています。

コットン・コーデル氏によれば、「Fisherman」はタダ魚が釣れて喜んでいる次元の釣り人を指します。つまり、魚を釣る行為そのものに喜びを見出している人々です。
一方で、「Angler」は釣りそのものに深い哲学や思考を持っている人々を表していると言います。彼にとって「Angler」は単なる釣り人ではなく、釣りを通じて自然や時間の美しさを味わい、釣りの技術や文化、そしてそれをどう継承するかをも考える高貴な存在なのです。
この表現は釣りに対する考え方を大きく変える視点を提供してくれます。釣りの楽しみ方にもいろいろな段階があり、「Fisherman」の喜びも決して否定されるべきものではありません。
しかし、「Angler」のように釣りを一歩深く掘り下げることで、新しい価値や充実感を得られることをコットン・コーデル氏は示してくれたのです。
パンデミックが起こした釣りブーム! 釣り人はクズ? カッコイイ釣り人って?
2020年、世界中を襲ったコロナウイルスの流行。その影響で人々は感染リスクを避けるため、ソーシャルディスタンスを保ちながら生活する必要に迫られました。
この新しい生活様式は、屋外で行うキャンプやアウトドア活動への注目を集め、その結果としてアウトドアブームが広がるきっかけとなりました。特に海釣りは多くの人々にとって新たな趣味として選ばれ、自然と触れ合いながら安全に楽しめる活動として人気を博しました。
このアウトドアブームは、経済的には一時期の活性化に大きく貢献し、アウトドア業界を支える重要な推進力となりました。しかし、ブームの特性上、様々な価値観を持つ多くの人々が一過性で釣りに参加するため、しばしばマナーに関する問題が浮上します。
例えば、ネット検索において「釣り人クズ」や「釣り人うざい」といったネガティブなキーワードが目立つ一方、「釣り人カッコイイ」というポジティブな表現も同時に検索されている現状があります。
ネガティブな側面では、ゴミのポイ捨てや立ち入り禁止エリアへの侵入など、マナー違反が問題視されています。一方で、ポジティブな側面としては、常識的な行動を心掛け、周囲との調和を大切にする釣り人が評価されています。このような両極端な評価は、釣り文化全体に対する課題でもあり、教育や啓発の必要性を感じさせます。
バス釣りについて言えば、このアウトドアブームに乗ることはなかったため、個人的には安堵しています。しかし、この騒動を目の当たりにすると、海釣りがかつてのバス釣りブームの末路と同じ道を辿る可能性を懸念する声も多いのではないでしょうか。
かつてのバス釣りブームでも、ブーム終了後の影響でマナーや文化が大きく揺らいだことを思い返すと、同じ過ちを繰り返さないためにも、海釣り文化の成熟が求められるのかもしれません。
釣り具のパッケージにポイ捨ての注意喚起がされていない不思議!
あるバス釣りYouTuberが、バス釣りメーカーのルアーのパッケージに「ゴミを捨てないように」といった注意喚起が記載されていないことに憤りを感じているという話がありました。
この指摘は非常に興味深く、確かに現状としてルアーやワームのパッケージにマナーに関する注意書きがないメーカーも存在します。釣り具メーカーすべてがこのような注意喚起を行うべきかどうかは議論の余地がありますが、こうした配慮がゴミを減らすきっかけとなる可能性があることを考えると、非常に意義深い提案と言えるでしょう。
注意書きがどれほど効果を発揮するかは不明ではありますが、その一文がきっかけで環境への配慮が広まり、ゴミが減少するのであれば、それは素晴らしい成果です。
また、近年では「Sustainable Development Goals(SDGs)」、すなわち持続可能な開発目標が社会的に注目を集めており、企業としてこれに取り組む姿勢が求められています。釣り具の製造者や販売者も、自身が一人のアングラーであるという自覚を持ち、環境に優しい選択を行っていくべきではないでしょうか。
さらに、日本はどこの海や川、そして沼や池でも無料で釣りが楽しめるという特性があります。これは釣り人にとって非常に恵まれた環境である一方で、釣りという活動の敷居が低く、マナー問題が発生しやすい背景にもなっている可能性があります。
釣り文化が発展するにつれて、アウトドア先進国としての立場を目指す時期が来ているのかもしれません。そのためには、釣りを楽しむ人々全員がマナーや環境保護について深く考え、行動に移す必要があります。
おわりに
今回は釣り人を英語で訳すとなんて言うのかという所から話を発展させてみました。何でこんな記事にしたのかと言うと「IKE-Pさんの新年のブログ記事」を読んで考えるところがあったからです。
バス害魚問題から大分と時間が流れ駆除はされ続けて現在のバスフィッシングの成れの果てがあります。何が違ってしまったのかは置いといてこれから、何とかしないと本当に未来のバス釣りは面白くないものになりそうですね。
ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。
釣り人を英語ではAnglerと言います!Fishermanとの違いはナニ?の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。
では!! よい釣りを(^O^)/
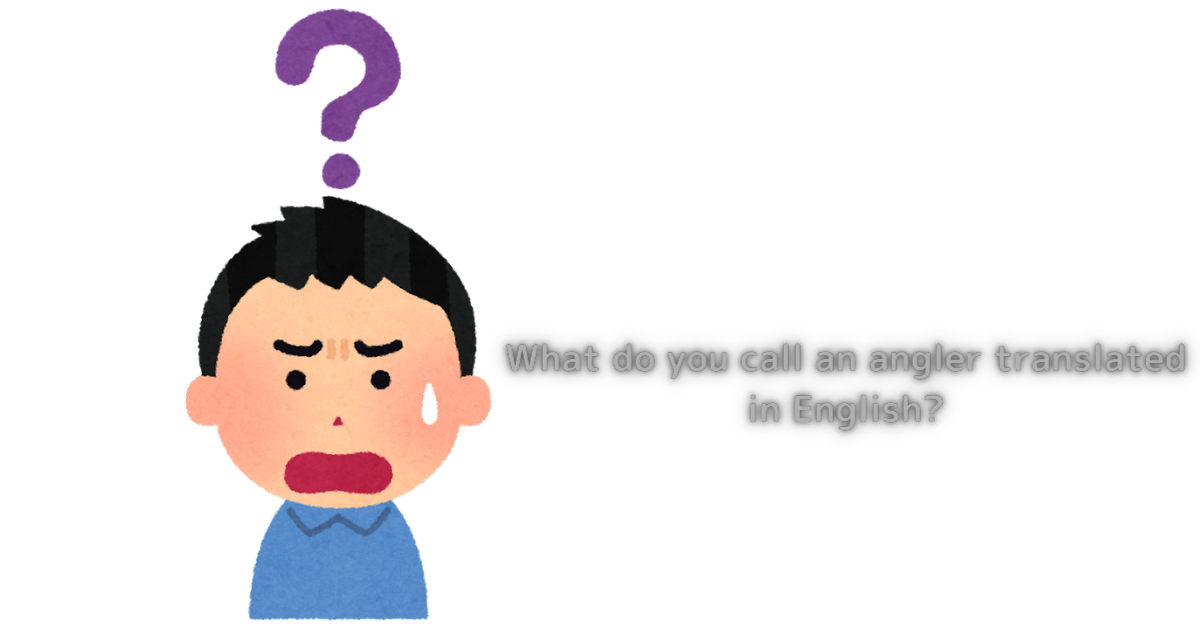
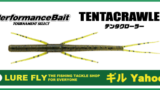


コメント
まぁ、、色々あるとは思いますが
ゴミは捨てないのが当たり前かと😅
バス釣りの未来については、
僕に出来ることを微力ながら
面白くなりそうな方に力を注いで
行こう、そう思っております😊
次男坊さんコメントありがとうございます😊
ゴミは捨てないのが当たり前という前提で釣りを楽しまれている
人がほとんどだと思いますが、稀に基準がズレた方が釣りや
アウトドアスポーツの現場に居たりするんですよね🤔
ゴミは良識のある釣り人が持って帰っているし拾うこともしてると
思いますが、もう少しルアーメーカーにも努力はしてほしいです😊